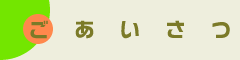 |
| |
 |
コラム |
|
| |
| |
| 同門会誌「淡成」に寄せて〜『淡成』考(平成13年4月) |
同門の一員となって16年以上になるというのに、考えてみると「淡成」の意味や謂れについて何にも知らない事にふと気付きました。ワープロで「たんせい」と綴って選択のキーを叩くと、随分いろんな「たんせい」があって、自分自身の小児科医人生を振り返り、感じ入ってしまいます。
入局当時はこざっぱりとした「端正」な出立ちで病棟に参上し、夢や希望に満ち満ちていたけれど、当直に継ぐ当直で次第に身なりは汚くなって、いったい自分が
男なのか女なのか(「単性」)もわからなくなる程バタバタ働いている内にヘマばかりしでかして、このままでは先輩の先生方が「丹精」込めて築き上げられた
伝統も台無しだと、あまりの情けなさにふと「嘆声」が漏れてしまう。ああこんなんじゃ早死してしまいそうだな(「短逝」そんな言葉はないかも知れません
が?)と、またまた「嘆声」。そんな自分の歩みが思い返されて来ます。
同門〜母校〜故郷などと思いを馳せ、どのように筆を進めようかとぼんやりと考えてみました。私自身は長崎生まれの長崎育ち(実家は医学部から歩いて5分)
で、大学時代は新聞配達をしていたこともあり休みを取って旅行をする機会もなかったので、大学を卒業するまでは関門海峡を超えて九州以外の地を訪れる事す
らなかった箱入り息子でした。ところが、入局後4年半経ったところで長崎県を離れ仙台の地で2年半、さらには日本を離れてアメリカ合衆国で8年間と、今度
は一転して放蕩息子のようでした。海外の地で自分の出身地について話をする際に、「長崎」というところはどういう処だろうかといろいろと考え込んでしまい
ました。アメリカ人にとって「長崎」は東京、京都、横浜、広島に次ぐ位に知名度がある街です。少なからぬ数の教養人は「長崎」が鎖国時代に唯一開かれてい
た港である事すら知っています。西洋式の医学の発祥の地である長崎にはその当時日本中から多くの医学者や医学生が訪れ、新しい学問を身につける興奮に高ぶ
る気持ちを抑えきれないでいたのだ〜と思いを馳せると、逆に今の長崎の姿に少しやるせなさを感じないでもありませんでした。
私が長崎大学に戻った後、学会などで学外の知り合いの先生方にお会いするとお祝の言葉を掛けていただきましたが、殆どの方から『「伝統ある」長崎大学医学部
に就任されておめでとう』という風な言われ方をされると、『ああ、「伝統ある」というのは「長崎」の枕詞のようなものだな』と思ってしまいました。時々自
分自身について自慢する事がないものだから、「俺の家はもともと藤原氏の(もしくは平家のでも何でもよろしいのですが)末裔でね」などと先祖自慢する人が
いますが、何だか「長崎は西洋医学の発祥の地」だとか何だとか言っていると、それに似ているなと情けない気が致します。(ところで、藤原氏やその他由緒あ
る家柄御出身の同門の先生方、他意は全くございませんので、御容赦下さいませ。)
外に出て(つまり国内でも全く長崎の同門の先生方の傘下にないところや、もちろん海外に出て)感じた事は、「(いい意味での)緊張感」と「新たな知識や技術
を修得する新鮮な喜び」です。これまで当たり前に思っていた事が当たり前でなく、思いもしなかった事が当然のように行われる〜何故そうする方がいいのか?
その根拠は?さらに改善する余地はあるのか?臨床の場でも研究の場でも、そういう「ショック」を与えられた事が自分自身を鍛えていく糧になったと思いま
す。おそらく昔長崎の地で西洋医学を学んだ医学の徒らは、私自身が感じたこのショックの何百倍もの刺激を受けたに違いありません。
長崎はまた医学の発信基地になりうるのか?それには実に多くの課題が積み上げられています。長崎が発信する力を有する為には、まず充分に自らを充電させなけ
ればなりません。充電に必要なもの、それは感電する事〜ショックを受ける事です。自分達にはない新しい知識や技術やシステムを見聞し、いいところは積極的
に取り入れ、さらに改善していく。緊張感を持って仕事に励み、あやふやな事をあやふやのままには放っておかないで、真剣にお互いに討論していく。それがプ
ロの仕事場であると信じています。少なくとも私自身は、真剣に渡り合った相手である程、公私ともに深く長い親交を持っており、仕事の場での「和」というも
のを「真剣勝負をしない事」と勘違いする事は、その人にとって大変不幸な事だと信じています。おそらくシーボルト門下であれ何であれ、長崎が日本の雄たり
得た頃のいわゆる「同門」というものは、日本国中から集まって来た秀英達が、師とともにそうした真剣勝負を繰り広げていた場であったに違いありません。
21世紀に向けて長崎がさらに躍進し、過去の栄光を取り戻す為には、周囲を山に囲まれて狭い視野の中でつまらない事ばかりに目を向けたり、ぬるま湯の中につ
かってほんわか気分でいては無理です。目先の利益や眼前の人の反応がかりを気にしながら行動していては、海を埋め立てて土地を拡げたと喜びはしゃいで、実
は外へ羽ばたく為の港を縮めてしまった事に気付かなくなってしまいます。
「淡成」の「淡」という文字には、血の濃さに対する水のさっぱりとしながらも懐の深い様を感じます。出身地だの学閥だの肌の色だの言葉の違いだのにこだわらず
国内外から多くの人々を受け入れて来た長崎の土地柄を偲ばせる言葉にも思えます。そして様々な経歴を経てこの長崎の地で、「小児の心身の健康福祉」という
共通の目標を掲げて、共に協力し競い合う同門の集まりに相応しい名前だとも思います。
「淡」という文字はそういうさっぱりあっさりの様を呈しながら、「炎」のような情熱を内に秘めています。この新生「淡成」が、そういう懐深く、内に情熱を秘めた集まりであらん事を願って止みません。 |
|
|
|
|