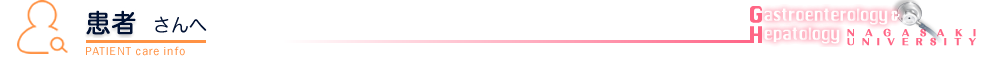診療紹介 (2.肝疾患診療班)
肝疾患診療は、消化器内科発足に先立ち2008年6月より第一内科、第二内科の肝臓班が合同して行っている。
肝疾患は慢性疾患であり、肝発癌と肝不全を終末期には引き起こす。すなわち肝疾患診療はその初期段階である慢性肝炎の時期から終末期に亘り、総合的に診療できる設備と専門性が要求される。
また近年の医療の進歩は肝移植というすばらしい方法を長期生存不能と判断された末期肝疾患の方々にもたらした。当然、我々内科医も肝移植に対する充分な知識が必要になり、そして移植前後の医療に積極的に関与していかなくてはならなくなって来た。
最近注目されている生活習慣病も肝疾患を引き起こすことが知られており、以前脂肪肝として肝臓専門家には見向きもされなかった病態の中に肝硬変、肝癌に進行する非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)と呼ばれる症候群が存在することが分った。
以上の様な肝疾患の現況に対応して我々のグループは積極的に肝疾患の診断と治療に取り組んでいる。
肝疾患は慢性疾患であり、肝発癌と肝不全を終末期には引き起こす。すなわち肝疾患診療はその初期段階である慢性肝炎の時期から終末期に亘り、総合的に診療できる設備と専門性が要求される。
また近年の医療の進歩は肝移植というすばらしい方法を長期生存不能と判断された末期肝疾患の方々にもたらした。当然、我々内科医も肝移植に対する充分な知識が必要になり、そして移植前後の医療に積極的に関与していかなくてはならなくなって来た。
最近注目されている生活習慣病も肝疾患を引き起こすことが知られており、以前脂肪肝として肝臓専門家には見向きもされなかった病態の中に肝硬変、肝癌に進行する非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)と呼ばれる症候群が存在することが分った。
以上の様な肝疾患の現況に対応して我々のグループは積極的に肝疾患の診断と治療に取り組んでいる。
| 慢性肝疾患を入り口で治療する |
| 現在肝癌の原因となる最大の原因はC型肝炎ウイルスである。国民病として政府も積極的に治療に取り組みが出来る体制を整えようとしている(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/index.html)。治療方法はインターフェロン療法が中心であるが、以前と違い注射は週1回(ポリエチレングリコール負荷インターフェロン、略してペグインターフェロンです)でよくなっており、リバビリン内服薬を併用することにより、難治性である血清型1型高ウイルス量の群の治癒率は以前の1割台から5割を越えるようになってきた。さらに今後も新たな薬剤の開発も報告されている。 我々はインターフェロン治療を積極的に導入しており、2008年は50例のC型慢性肝炎の方にインターフェロン治療を新規導入した。再治療、高齢、肝線維化進行例、以前副作用で中止した方などが多いのが特徴である。 今後も地域の先生方と協力してC型慢性肝炎撲滅のため邁進していくつもりである。 |
| 肝癌を早期に発見し治療する |
| 残念ながら慢性肝炎の治療が奏功しない場合、肝癌の早期発見のため血液検査(AFP、PIVKA-Ⅱ、AFPL3分画は我々の先輩方が肝癌との関連を見つけNew England Journal of Medicine誌に掲載されました)、エコー、CT、MRIを組み合わせて効率よく肝癌を早期に発見し、治療に持っていくようにしています。 肝癌治療は肝機能によって大きく治療法がことなり、放射線科、肝臓外科の先生方との連携が欠かせません。長崎大病院では2008年2月より放射線科、外科、当科の合同で肝癌カンファを行い、総合的に治療法を判断していくようにしている。新規抗癌剤も登場する肝癌治療である、可能な症例ではより根治的な治療を、そうでない場合にはQOLの維持を目的に治療を選択したいと考えている。当班ではラジオ波焼灼療法、化学療法に積極的の取り組み、腫瘍血管塞栓療法は放射線科、手術や移植は外科に依頼して治療してもらっています。 2008年の初診肝癌は46例、うちラジオは焼灼療法10例、血管塞栓療法17例、外科的切除5例、肝移植3例、化学療法3例、重粒子線紹介1例を行いました。 |
| 肝不全対策を行う |
| 肝不全とは肝細胞の減少により引き起こされる肝性脳症、腹水、倦怠感、不眠、栄養状態悪化などの症状の総称である。かつては対応することが困難な状態であったが、近年幾つかのおおきな進歩が見られている。 まず上げられるのは栄養療法の進歩である。肝硬変症の栄養評価が重要であることは知られていたが実際分枝鎖アミノ酸製剤を補充することにより、生命予後の改善が報告されており、当班でも栄養評価と栄養療法は積極的に行っている。長崎大病院栄養管理室との連携を重視している。 究極の肝疾患治療は肝移植である。肝不全に対する治療も同様である。残念ながら現在は生体肝移植が中心であり、ドナーとしてご家族の中から名乗りを上げられた方、年齢や感染症などの問題をクリアできた方が対象となる。長崎大学移植・消化器外科では既に98例(2009年3月始)の生体肝移植を行っており、我々も肝移植の情報を対象の方々に提供し移植医療に参加している。 |
| 生活習慣病と肝疾患の関係 |
| C型肝炎ウイルスやB型肝炎ウイルスと違う原因の肝硬変、肝癌症例が増えてきている(研究の頁をみてください)。その中には以前より知られているアルコール性肝疾患以外に、肥満歴があり耐糖能異常をもつメタボリック症候群の部分症といえる症例が確実に存在する。これらの原因が非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)でる。 当科では以前よりこの病態に注目し肝生検を積極的に行ってきた。メタボリック症候群と同様まずは体重減少が必要な疾患であるが、薬剤投与や瀉血療法なども試みられている。当科でもNASHに対しては厳重な管理を行い肝線維化の進行、肝発癌の診断治療を行っている。 |
| 肝移植について |
| 肝移植は末期肝臓病に対する唯一の根治的治療であり、国内で4000例以上(2006年末)が行われ、現在では末期肝疾患の標準治療となっています。 当院でも118例(1997年8月から2010年3月まで)の肝移植を施行しており、2009年は年間20例の肝移植を施行しました。 当科の特色 当科は国内でも少ない肝移植を診る内科です。 ご紹介いただいた患者さんの移植適応の判断や適切な移植時期の設定、またドナーの適格性の判断など内科的立場から検討し、移植外科への橋渡しをしています。 成人の肝移植症例の全例が術前管理を目的として当科入院となります。 また、内科での治療の経験を生かして術後も積極的な抗ウイルス治療を行っております。
最後に - 肝臓病を患っておられる方へ 肝臓の治療は日々進歩しておりますが、残念ながら一旦肝硬変まで進行してしまった肝臓をもとの状態に戻すことはできません。また、肝臓癌も初発からの5年生存率は約50%であり、肝癌を発症してしまった場合はその予後は厳しいと考えざるをえないのが現状です。現在の日本では脳死による臓器提供が少ないため、ドナーの問題など数多くの問題点があるのも事実ですが、現時点では肝移植が肝疾患に対する究極の治療法であることは間違いありません。従って、ある程度長期に肝臓病を患っておられる方であれば、一度は肝移植という治療について検討して頂きたいと考えております。 |