| 大仁田 賢 |
|---|
|
今回、「海外派遣による自立した若手生命医療科学研究者育成支援プロジェクト」という企画で2ヶ月間アメリカのMayo clinicに短期留学の機会をいただきました。Mayo clinicを選んだ理由は、まず胆膵領域(特にEUS)の勉強をしたいと思ったこと。EUSで有名な病院のうちどこに行くかと考えた時に、ダウンタウンに近く車なしでも生活できること、先輩の磯本先生、同僚の赤澤先生が以前留学しており、磯本先生の橋渡しで比較的簡単に受け入れをOKしてくれたことがあります。磯本先生ありがとうございました。 |
|
| 宮明 寿光 |
|---|
|
平成9年入局の宮明です。みなさんお元気でしょうか。 |
|
| 赤澤 祐子 |
|---|
|
今年9~10月にかけて、「海外派遣による自立した若手生命医療科学研究者育成支援プロジェクト」という企画でMayo Clinic のGastroenterology and Hepatology research 部門で基礎研究をしてきました。ここは2009年まで留学していたところでした。 行ってみると、2年前に去ったロチェスターは変わっておらず、友人や同僚たちも暖かく迎えてくれました。財布を忘れてスタバに行くと、ただでコーヒーをくれるようなおおらかな町です。(知らない人とすれ違っても微笑み合うくせがついてしまうので、日本に帰ると、変な人と思われます。) |
|
| 三馬 聡 |
|---|
|
2010年8月より、米国オハイオ州コロンバスにあるオハイオ州立大学Comprehensive Cancer Centerへ後輩の柴田先生のあとを引き継ぐ形で留学させていていただいている三馬です。私は大学卒業後、長崎大学第一内科へ入局、5年目より消化器内科を専門として臨床に従事していましたが、7年目より大学院生として大学に戻り、大学院卒業時には無事博士号も取得できました。ただ再び臨床に戻る前に、もう少し実験、研究をやりたい気持ちがあり、今回留学させていただくこととなりました。大学在学中は多くの面で諸先生方に御迷惑ばかりおかけしていましたが、この度は快く留学へと送り出していただき本当にありがとうございます。実験、研究をもう少しやりたい気持ちとともに、今回留学したいと考えさせられたもう一つの大きな契機は、2年前のサンフランシスコで行われたAASLDに参加したことでした。今まで写真やテレビでしか見たことがない海外の人々、風景が目の前にあり、何も分からないことだらけであることが、非常に不安であるとともに逆に非常に刺激的に感じました。世界が広がる、とはこのことだと、よくいえば冒険心です。留学前大学在学中に後輩に、「留学って不安じゃないですか?」と聞かれ、「まぁ不安だけど、ドラクエで言えば船を手に入れるような気持ちだよ」などとうそぶいていましたが、これは半分は本当です。 |
|
東日本大震災レポート(米国オハイオ州から)
私は今回、東北大震災を留学中のオハイオ州の地で知った。こちらでも甚大な被害について繰り返し報道され、震災数日は震災の報道一色であった。今なお、原発の問題については専門家を交えて現況に対する分析がニュースで報道されている。我々の日常生活は、関東地方などからの郵送が制限されているなどのごく限られたものであり大きな変化はなかったが、私が働くオハイオ州立大学、及びオハイオ州では、様々な催し、募金活動が行われている。今回の大震災における周囲の反応、及び自身が感じることについてご報告いたします。
大震災直後より、アメリカ合衆国、及びオハイオ州、オハイオ州立大学にて、多くのガレージセール、コンサートなどの催し、募金活動が行われており、オハイオ州立大学、及びオハイオ州立大学日本人会を通じ、多くのメール、案内が届いた。下記以外でも多くの活動が現在も行われている。
オハイオ州立大学での募金活動
3/24/11: Candlelight Vigil (ともしびの集い), Thomas Worthington High School
3/14-18/11: Sup4/25: Cranes for Kids: Giving Hope to the Children of Japan (折鶴プロジェクト)
アメリカでも震災直後より、テレビでは連日震災関連のニュースが流されていた。壊滅的な被害を受けた被災地の映像が繰り返し流されるとともに、特別番組も組まれその被害の大きさについて大々的に報道されていた。また震災直後、すぐにオバマ大統領や政府高官と思われる人々より、日本支援の姿勢が打ち出されていた。その一方、甚大な津波による被害と比較し日本の建造物の倒壊の少なさにも触れ、耐震性の高さについて驚きをもって報道されていたようである。耐震技術に優れた日本の建物でなければより被害は拡大していたであろう、と言った論調であった。被害の状況が詳細になるとともに、次第に原発問題がクローズアップされていった。日本政府の対応に関しては残念ながらあまり好意的に報道されてないような感じである。日本政府が原発周囲12マイルの避難勧告範囲を設定したのに対し、アメリカ政府は50マイルに設定していることも報道されていた。原子炉の状況は図説も交え詳細に報道され、地震より約一ヶ月以上経過した今日でも、専門家とともに現況分析、チェルノブイリ原発事故との比較などが行われている。アメリカのある州では、ごく微量の放射能が検出されヨウ素の買い占めが起きていることが報道されていた。これについて医師がもともと極微量は検出されており、今回検出されたものも極微量でヨウ素の必要性は全くない、と正していたが、放射能についてはアメリカ人も非常に敏感になっていることが伺われる。ちなみにテレビで見る限り、被災市民への取材はほとんど日本人に対しては行われておらず、日本に在住するアメリカ人に対する取材がほとんどであった。
職場の同僚は、日本の建物の耐震性の高さに感心していた。そしてなにより、暴動、略奪が起こらない、日本人の混乱しない、我慢強い、秩序だった行動に非常に驚いており、アメリカではあり得ないよ、と話していた。私が通っている英会話の先生も、クラスのディスカッションの中で、”Sympathy for Japan, and Admiration(日本への同情と尊敬の念)”と書かれたニューヨークタイム誌のコピーを配り、そのことにについて賞賛されていた。多くの国々の人々と行動を共にしてみると、改めて日本人と外国人の国民性の違いに気づかされるが、その中で日本人の自己主張をしない消極的な国民性といったものは決して評価されないよう感じる。沈没しつつある客船の船長は、女性と子供以外は船に残るように求める時、米国人には「あなたは英雄になれる」、英国人には「残れば紳士です」、イタリア人には「女性にもてます」、そして日本人に対しては「みんな残ります」と言う、といった有名なジョークがあるほどである。ただこの国民性は、他人を尊重し、我慢強いといった日本人の国民性とまた表裏一体のものでもある。その国民性によって保たれた震災における一般市民の秩序が非常に評価、賞賛されることに日本人として私は非常に誇らしさを感じたが、その一方で少し不思議な感じもした。
今でも震災の話は同僚との間で時に話し、これから日本はどうなるのだろうかと言う話になる。また原発の問題が将来の復興に対する大きな障害であることは周知の事実であり、関心も高い。その中で今後の震災からの復興を願う気持ちというものは、日本人も外国人に何ら相違ないのは間違いないようである。最後に、震災直後にいただいた英会話教室の先生からのメッセージ、および職場の同僚からのメッセージを添付いたします。
At this time, I would like to extend my sympathy and condolences to you on the current tragedy in Japan. You are safe here, but I hope that all of your family is safe. The pictures on TV are unbelievable, something out of a Hollywood movie. The suffering and destruction are more than anyone can bear, yet I see the Japanese people have courage and are working closely together to help each other. Know that the world will help and that the Japanese people are resilient and will come through this tragedy stronger than ever.
I knew the recent Japan earthquake and tsunami right after it happened. I am very sorry about this and hope that Japanese who suffered from the disaster can recover as soon as possible. Congregations in my Chinese Christian church in Columbus are praying for the victims and initiated a donation designated to help Japan. I am also aware of the leakage of nuclear radioactive material as a result of the earthquake. I wish this issue can be solved soon and the damage can be contained.
Sincerely yours, |
| 「プロフィール」ページ |
| 平成14年久留米大学卒業 柴田 英貴 |
|---|
|
慌しく長崎を去った2008年9月が随分昔の事に感じるようになりました。当時の第一内科消化器班の皆様に盛大な送別会をしていただいた際には、胸にこみ上げるものがあり、あれだけ留学すると言い続けてきたにも関らず、長崎を離れたくないと思った事を懐かしく思い出します。当時の苦しい医局事情を思うと、快く私を送り出してくださった先生方には本当に感謝しています。 |
| 「プロフィール」ページ |
| 平成10年長崎大卒業 松本 幸次郎 |
|---|
|
アメリカ臨床医経過報告 【2010年4月】 |
| 【2009年6月】 長崎大学消化器内科誕生及びホームページ開設にあたり、医局長より直々に「研究留学をして、その後そっちで医師になる決意をし米国医師になるまで」を書いてほしいとのご依頼をいただきました。教室にとっては放蕩三昧の私が留学記など書く資格はないと思いますが、手前勝手な行動の言い訳として読んでいただければ幸いです。 医師になろうと決心したのは高校2年生でした。まだ純粋であった私は青年海外協力隊のように発展途上国で働こうと決め、医学部進学を決めました。ですが、私の欠点である長期的計画能力欠如症候群(要は行き当たりばったり)がその後の私の人生に付きまとっていくとは当時は思ってもおりませんでした。医学部生になると高校生の頃の夢などすっかり忘れ去り浜口町で飲み歩き、卒後は長崎大学第一内科に入局致しました。その後、手技が多く面白いと思った消化器内科医を目指すと同時に、いずれは取得しないといけない状況であった博士号取得を早く済ませたいとの不純な動機で、卒後4年目で大学病院に戻って参りました。 大学に戻る前に勤務していた市中病院では消化器内科医を目指していたものの、できるだけ幅広い疾患とあらゆる手技に対応できるようになりたいとの思いが強く、医局や専門の垣根を超えてさまざまな先生方に教えを請いました。大学院在学中の天草でのアルバイト勤務の際も、島ということがあり、小児科、整形外科、皮膚科、泌尿器など様々な疾患を見る機会があり面白さを感じておりました。 そんな中、幸い学位論文が3年で出来上がり、大学院生活が1年残っていたため、先のことはあまり考えずにせっかくだから研究の実績を使って海外生活を体験してみようと思い、アメリカはシカゴのノースウエスタン大学に2年の予定で留学致しました。実際にアメリカの大学病院にやってくると、私の知らない世界がそこにはありました。多くの外国人医師が第一線でアメリカの医療を支えており、また外国人であるにもかかわらず、世界一であろうアメリカのレジデント教育の恩恵を存分に受けておりました。完成されても尚進歩していく教育システムと指導医の数など圧倒的な人的経済的資源の豊富さには正直圧倒されました。 また、こちらの医療を知るうちに、あらゆる疾患及びあらゆる患者に対応する家庭医療科に興味を持つようになりました。家庭医療科の第一心情である患者さんとの関係第一という姿勢も、患者さんと過ごす時間に生きがいを感じる私のスタイルと正に同じだと感じました。また非常に興味深いのは、アメリカの医師は勤務医、開業医問わず発展途上国への医療活動に積極的に参加しており、身近な医師がそれこそ日本と比較すると気軽な感じに見えるほど発展途上国に数週間行ったりしています。そこで、またまた先のビジョンが見えないにもかかわらず、アメリカで臨床医を目指す決断をしてしまった訳です。ですが実際は思うようにいかないもので、よくよく考えてみると(というかよく考えなくても私を知っている友人にとっては周知の事実ですが)医学生の頃の私は再試の嵐で友人からは再試リーダー略してリーダーと呼ばれており、自他共に留年せずによく卒業できたなと思われたその私が英語で外国の医師免許試験を受けるなど無謀な挑戦であることは火を見るより明らかでした。結局、研究業務以外の時間つまり夜と早朝は机にかじりつき、週末も図書館に行ったりと余暇が全くない生活を余儀なくされ、アメリカに来て多少なりともゆったりとした家族の時間を過ごせると思っていた妻の期待を大きく裏切り、日本にいた頃と変わらない仕事時間になってしまいました。研究留学と言う爪に火を灯す様な耐乏生活の中、夫は勉強ばかりで、海外で誰に頼れるわけでもなく乳飲み子を抱えた妻の生活は非常に過酷だったと思います。話は逸れますが、妻帯者がアメリカで長く生活していくキーワードは「妻」で間違いないと思います。でなければ私はとうの昔に日本に戻っています。 基礎医学、臨床医学、一日で12人の模擬患者さんを診察し診察ノートをその場で提出するというストレスフルな実技試験の3つの試験をなんとかクリアしました。その後アメリカでの臨床経験がポジション獲得には非常に重要であるということを知り、コネのない私は当たって砕けろで面識もない方々に連絡を取り臨床実習をさせてもらいに、数週間あるいは週末を使っての病院実習をさせてもらいました。見ず知らずの私に手を差し伸べてくださった先生方の優しさは非常にありがたく、私の目標達成に非常に大きなポイントとなりました。更には、ビザの問題などで計画が1年遅れたりもしたのですが、なんとか今年6月よりイリノイ州の州都、リンカーン大統領ゆかりの地スプリングフィールドのSouthern Illinois University家庭医療科にて3年間のレジデント生活を始める運びとなりました。 その時その時に自分の興味のままに進路を決めてしまい、なぜか今はこのような形で医療に関わっております。一流のレジデント教育システムの中で勉強でき、患者さんと一番密接に関わりあらゆる疾患を診る家庭医療科、高校生の頃の目標を思い出させてくれるアメリカの医療活動、そういった経験を通して今後またやりたいことが具体化されてくるのかもしれません。以上の様に私の医師人生は正に右往左往しておりますが、一貫していますのは患者さんが第一ということでしょうか。たまの臨床実習の際に患者さんと話をしていると「あぁ、ここが私の居場所だよな」と居心地の良さを感じる自分に何度も気付いたのですが、裏を返せば研究留学のお陰でその事が再認識できたのかもしれません。ですから、アメリカで臨床医を始める大きな不安はありますが、同時に臨床に戻れるという嬉しさがあります。 こちらに来てから何度となく長崎大学で消化器内科医として働いていた当時のことを思い出すのですが、私の心の中に染み付いている一つ言葉があります。臨床、研究、学生教育など多忙な生活の中で目の前のことをこなすことで精一杯の毎日、中尾一彦先生がおっしゃっていた「患者さんが第一。実験中でもなんでも患者さんに何かあったときはやってる仕事を投げ捨ててでも患者さんの所に飛んで行け!!」という言葉です。消化器班で身に付けた心は遠くアメリカにいても常に臨床医としての私の心の中心に位置しています。 本来であれば、アメリカで習得した研究技術を長崎大学消化器内科に持ち帰るのが私の使命であるにも関わらず、中尾一彦教授、市川辰樹先生はじめ消化器内科の先生方に「頑張って」とおっしゃっていただける私は幸せ者だと思います。 最後ではありますが、今後の長崎大学消化器内科の更なる発展を心より願っております。乱文失礼いたしました。 |

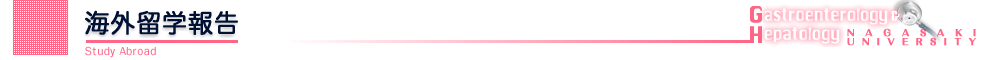






 久しぶりにラボに行くと、2年前にドアのところに忘れていた自分のスカーフがそのままかけてあったのにはちょっと驚きでした。ボスのDr. Goregory Gores(写真左)は、消化器のDepartment Chairでもあり、AASLD(アメリカ肝臓病学会)のオーガナイザーを務めたこともある、名の知れたscientistでもあります。ラボの主なテーマは肝細胞癌/胆管細胞癌における分子標的役の作用機序や脂肪肝の基礎実験です。ボスはアメリカ出身ですが、イタリア、ドイツ、スイス、インド, 日本など各国からのフェローやスタッフがいて、ほとんどが私のようなmedical doctorです。ちなみにスイスでは、消化器内科医の数が厳密にコントロールされていて、誰でもなれるわけではないらしいです。私たちは希望すれば勝手になれるので幸せですね。
久しぶりにラボに行くと、2年前にドアのところに忘れていた自分のスカーフがそのままかけてあったのにはちょっと驚きでした。ボスのDr. Goregory Gores(写真左)は、消化器のDepartment Chairでもあり、AASLD(アメリカ肝臓病学会)のオーガナイザーを務めたこともある、名の知れたscientistでもあります。ラボの主なテーマは肝細胞癌/胆管細胞癌における分子標的役の作用機序や脂肪肝の基礎実験です。ボスはアメリカ出身ですが、イタリア、ドイツ、スイス、インド, 日本など各国からのフェローやスタッフがいて、ほとんどが私のようなmedical doctorです。ちなみにスイスでは、消化器内科医の数が厳密にコントロールされていて、誰でもなれるわけではないらしいです。私たちは希望すれば勝手になれるので幸せですね。 



