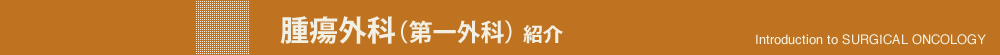ご挨拶
|
2024年3月1日より、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科腫瘍外科学分野の教授に就任いたしました。前教授である永安武長崎大学長の後任として、長い歴史のある当教室の主任教授に就任させていただいたことを光栄に思います。 これまでの伝統の上に、外科学教室を時代に合わせて進化させていくのが私の役割であると思っています。教育、研究、臨床のすべての面において、病院、医学部、大学そして地域医療に貢献できるように、教室一丸となって努力していく所存です。 長崎から日本の医療に新たな未来を発信できるように新たな形で臨んでいきます。 |
 |
|
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科腫瘍外科学分野 長崎大学医学部腫瘍外科(第一外科) 教授 松本 桂太郎 |
|