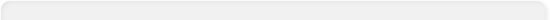 |
| ■ |
第1回歯科法医学若手セミナー(2016年10月8日・9日) |
岡山大学大学院医歯薬学総合研究
予防歯科学分野
内田 瑶子 |
私たちが普段生活している中で、「もし大切な人が亡くなってしまったら…」ということに思いを馳せることは、ほとんど無いと思われる。ただ、「もし…」はいつ生じるかは分からない。正しく「あの人だ!」と確実に見つけ出せる力が今の私にあるかと問われたら、元気よく「はい」と答えられないのが現状である。長崎大学とは異なり、私の所属大学歯学部ではまだ法医学の授業が始まっていないため、学生にとって法医学・法歯科医学はあまり縁のないイメージだろうと思われる。しかしながら、今もどこかで事件・事故は起こっているわけで、実はとても身近な医学なのかもしれない。今回の授業では法歯科医学の現在に至るまでの流れと死体現象に関して教えていただいたのだが、持てる医学知識をフルに活用して、日々従事されている先生方は本当にすごいなと考える。その先生方の中に、歯科医師だけれども加わっていければ…と思われた。 |
今回のセミナーでは今井先生と池松先生のご講義を拝聴しました。まず今井先生は長年この分野に関わってこられたので貴重な写真を多数お持ちで、一般の教科書では知る事のできない多くの事例を見させて頂く事ができました。特に雲仙普賢岳の被災者の写真は今回初めて拝見しました。あのように黒焦げとなってしまっては外表面からは個人識別どころか男女の区別さえ分からず、歯科所見が唯一の手掛かりであり、改めて歯科所見の有効性と重要性を強く感じました。池松先生のご講義で特に印象に残ったのは「3つの時計の矛盾点から死因を探る」というものでした。本学でも学生に死後経過時間の推定については講義していますが、死後硬直や直腸温低下等を個別に解説するのみで、それらを統合した形で実例に即して学生に考えさせるという内容ではありませんでした。来年度の講義に早速取り入れたいと思います。更に思いがけず法医解剖を見学させて頂き、大変得難い経験をさせて頂きました。医師の先生が複数いらっしゃって解剖を分担されており、かつ音声入力を活用して所見を記録されている様子を目の当たりにして、非常に効率的に法医解剖が行われている事に感銘を受けました。もし医師が教授1人だけで、口頭での所見を警察や助手の方がメモするという形でしたらもっと時間が掛かるだろうと思いました。また山下先生が手慣れた様子で口腔内所見を記録されていました。法医解剖に歯科医師が全く参加しない場合と比較すると、やはり歯科医師も参加した方が正確な口腔内所見が取れたり年齢推定をしたりする事ができ、より一層充実した解剖になるだろうと感じました。
今回のセミナーに参加して初めて得た知識が多くあり、来年度の講義で本学の学生にも還元していこうと思います。このような貴重な学びの場を設けて下さった先生方に心より感謝申し上げます。今後ともご指導の程宜しくお願い致します。 |
|
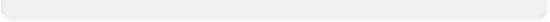 |
|

