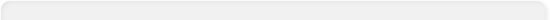 |
私は2016年4月から7月中旬まで、大学の研究室配属のカリキュラムにより、横浜市立大学医学部法医学教室にて研究を行ってまいりました。その一環として、7月5日から7日まで、長崎大学医学部法医学教室にて実習させていただきました。
初めに法医学教室の施設を見学しました。解剖のための設備のみならず、検査や研究のための設備も大変充実しており、初めて見るものも多く驚きました。具体的には、病理組織の包埋や染色が機械で全自動で行われる様子を見学したり、オモテ・ウラ試験を実験したりすることで、検査や研究の一端に触れられました。
さらに、2日目には検案と解剖も見学させていただきました。学生に先生方、加えて警察官の方々も解剖に携わり、同時に様々な検査が円滑に進められている様子にも驚きました。長崎大学では解剖の際に歯科医の先生が口腔内所見をとっており、私も少々お手伝いさせていただきましたが、口腔内所見のみで年齢をほとんど正確に当てていらっしゃるのに特に驚きました。
また、山本琢磨先生に乳幼児や小児の死亡に関する講義をしていただきました。加えて先生の取り組まれてきた研究についてもお話を伺い、また実験の一部を見せていただきました。私はこれまで研究にそれほど興味を持っておりませんでしたが、山本先生のされているような実務に役立つ研究は大変興味深く、研究の魅力に気づかされました。研究室配属が終わり、臨床の講義が再開するところですが、基礎医学も十分復習しなければならないと身が引き締まる思いです。
この3日間で全国屈指の規模を誇る法医学教室の実務の様子を十分に見学させていただくことができました。私は将来の選択肢の1つとして法医学者を検討しておりますが、本実習で法医実務の幅広さと深さを実感でき、法医学に対する興味がよりいっそう深まりました。
最後に、本実習を快諾してくださりました池松和哉先生、また長崎大学法医学教室の皆様に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。 |
通常業務でご多忙にも拘らず、3日間にかけて実習見学をさせていただけたことにまず紙面をお借りして御礼申し上げます。私が実習見学を希望した経緯には自身の研究内容が関係しています。横浜市立大学では4年生の前期にリサーチクラークシップというカリキュラムが組まれており、各々の配属教室で約4ヵ月間、研究活動を行います。私は当大学法医学教室に配属され研究活動を行いました。その際に扱ったテーマがSIDSに関するものであり、長年研究されているものでしたが研究内容の難しさに直面し行き詰っていました。そんな折に指導教官である井濱教授から長崎大学で行われているSIDSの原因遺伝子研究のお話を伺い、元々横浜市立大学と長崎大学の間で研究協力がされている背景もあったことから興味を抱き、今回の実習見学の実現に至りました。
まず教室内施設を拝見しましたが、規模の大きさ、業務別の豊富な教室員が印象的でした。実験機器に関しては標本作成の全自動化や、染色や解析にまつわるものも充実して研究環境が整備されている印象を受け、解剖実務が中心である当大学との違いを感じました。
次に長崎大学では当大学と違い検案業務も担っているということで、ちょうど検案業務と解剖業務の両方を見学する機会をいただきましたが、業務の丁寧さと警察の方々との関わりに注目しました。解剖実務の音声認識ソフトであるAmiVoiceについて当大学とは違い、長崎大学の場合は臓器別だけでなくさらに項目が細分化され、より詳細な解剖結果記録を残せるようになっていました。さらに入力者が複数でリンクされる状態になって、各業務者が解剖結果の同時入力ができ、円滑な解剖業務が実現されていました。警察の方々に関しても積極的な解剖業務の参加が見受けられ、地域性の違いを目の当たりにしました。
そしてSIDS研究に関しては中心である山本琢磨講師から基礎から最新の動向まで講義を受け、乳児組織から抽出したDNAを次世代シークエンサーにかけて遺伝子解析するまでの流れは短期間であるが、結果に表示された遺伝子変異が致死的かどうか判断するのは人間であり、過去の論文やデータから総合的に判断しなければならない長期間の業務であるという事実に、研究意義の醸成とデータ蓄積の必要性を感じました。
当初の目的は遺伝子研究が中心でしたが、実習見学を通じて大学間での法医業務自体の特色の違いに非常に驚きました。法医学も地域性を帯びている故にこのような違いが生まれているのであり、統一するのではなくこのような実習見学をはじめとした大学間の連携が非常に有意義であると再認識しました。このような機会をくださった池松和哉教授、山本琢磨講師をはじめ、長崎大学医学部法医学教室の皆様に改めて御礼申し上げるとともに、自身の研究をより深めていきたいと思います。 |
|
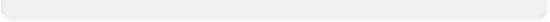 |
|

