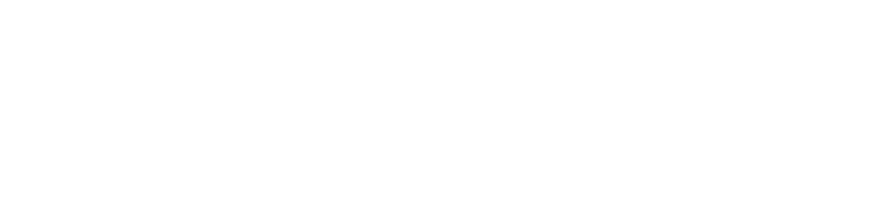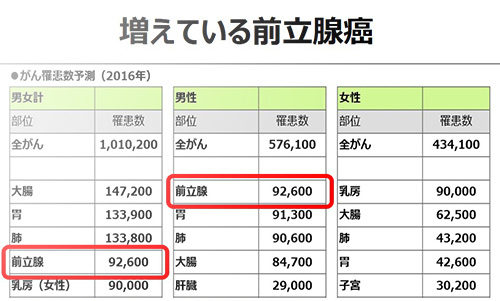腎がん(腎細胞がん)
腎がん(腎細胞がん)とは
人間には肋骨の下の高さでお腹の中やや背中側に腎臓が左右1個ずつ存在します。
ソラマメのような形をした、成人の握りこぶしよりもやや大きい臓器である腎臓には、血液によって運ばれてきた体内の老廃物をこして、不要なものを尿として排泄する働きがあります。その他、血圧をコントロールするホルモンや血液をふやすホルモンを作る機能や、ビタミンの働きを活発にする機能があります。
腎臓には尿細管という細い管があり、ここでは糸球体という細い血管でつくられた尿のもとから水分やさまざまな物質を吸収したり老廃物を排泄したりして尿をつくります。この尿細管の中に発生したがんを、一般に腎がん(腎細胞がん)と呼びます。
腎がんは60-70歳が好発年齢であり、10万人当たりの発生率は男性で33.7人、女性で15.1人くらいです。近年、腎がん患者の増加率は上昇しています。
腎がんの症状
腎癌の初期にはほとんど症状がありません。そのため近年では、健診での超音波検査やCTにより、偶然発見されるケースが増加しています。
進行すると、血尿、腹部のしこり、痛みが出現してきます。また全身症状として、体重減少、発熱、貧血をきたすことがあります。
腎がんの4人に1人は肺やリンパ節や骨などに転移が発見されるといわれており、これらも進行すれば呼吸困難や痛みなどの症状が出現することがあります。
腎がんが、一度転移すると、根治することは極めて困難であるため、早期発見のためにも健診を受けることが大切です。
腎がんの診断
超音波検査は簡便な検査で、健診でも施行できる検査です。超音波検査などで腎がんが疑われる場合は、必ず泌尿器科専門医の診察をうけましょう。
腎には腎がん以外にも腫瘍性病変が発生することもあるため(良性腫瘍、腎盂腫瘍)、より正確に診断するために造影剤を併用したCT検査が有用です。
また、病変の進展や転移を確認するために胸部CT 、MRI、骨シンチグラムを施行することもあります。がんの進行度によって、治療方針が変わるため、一般にステージ診断を行います(図1)。
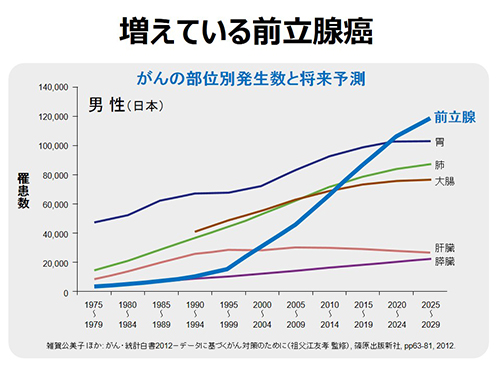
図1
特殊なケースでは皮膚から腫瘍に針を穿刺して組織を採取し、顕微鏡下に診断を行う場合があります。これを組織生検と言います。
腎がんの治療
転移がない場合
A:ロボット支援下腎部分切除術
がんが小さく(一般には4cm未満)、腎臓の正常な部位を温存することが可能な場合や、がんを腎臓ごと摘出した場合に腎不全による透析を要するケースでは、腎臓からがんの部分のみを切除する本術式が適応となります。
腎摘除術より技術的には難易度が高いですが、患者さんへの利益は大きいことが知られています。
C:根治的腎摘除術(開腹)
がんが大きすぎて(10cm以上)腹腔鏡下手術が困難な場合や、過去に大規模な腹部手術の既往がある場合、またがんが静脈に進展し下大静脈に至る場合は、上記A・Bが困難であるため開腹手術を要することがあります。
がんが小さい方で高齢、合併症などで手術が困難な場合や希望しない患者さんに対しては経皮的局所療法(ラジオ波焼却術)なども行っております。また、手術を行った後に病期分類や組織型によっては再発防止目的に薬物療法を行うこともあります。
がんが転移している場合
遠隔転移がある場合、薬物療法が中心となります。患者さんの加療歴、組織型、全身状態、効果や副作用を考慮し薬剤を選択します。以下は代表的な薬物になります。
分子標的治療
がんの増殖や血管の増殖に関わる因子を抑えることで、抗腫瘍効果を発揮するものです。内服薬での治療が中心で、多くの方は通院で治療を行っています。
免疫チェックポイント阻害薬
がんが免疫機構から逃れる機序に対し、それを阻害することで、リンパ球等ががんを攻撃するような治療となります。
患者さんによって、がんの悪性度や進行度が異なるため、これらの治療効果は一定していませんし、適している治療方法も異なる場合があります。また、治療経過によって、次々に治療薬を変更していくこともあるため、詳細な治療方針につきましては、個別に検討する必要があります。