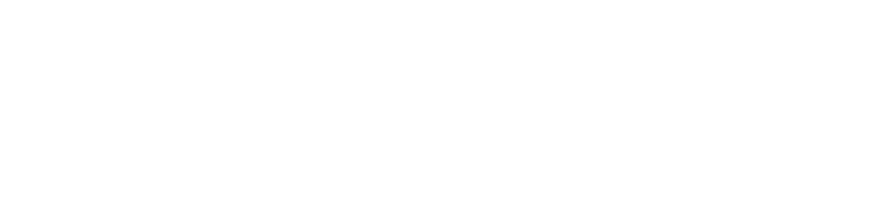泌尿器疾患
排尿障害
(前立腺肥大症、過活動膀胱、神経因性膀胱、尿失禁、骨盤臓器脱)
排尿障害とは
排尿障害とは膀胱に尿を貯め、貯まった尿を体外へ排泄するという排尿サイクルの過程に異常をきたす状態のことを指します。
排尿サイクルの乱れは大きく分けて以下の2つに分けられます。
排尿障害
- 排出障害(尿をうまく出せない)
- 蓄尿障害(尿をうまく貯めれない)
排尿障害の原因疾患としては主に以下の疾患が挙げられます。
| 排出障害 | 前立腺肥大症、神経因性膀胱(脊髄疾患、脳血管疾患、糖尿病など)、重度の骨盤臓器脱(膀胱瘤、子宮脱)、骨盤内臓器の手術後(直腸がん、婦人科がん)、現在内服中の薬剤の有害事象など |
|---|---|
| 蓄尿障害 | 過活動膀胱、肥満などの生活習慣病、神経因性膀胱、間質性膀胱炎、軽度の骨盤臓器脱、膀胱炎、膀胱結石など |
高齢の男性では前立腺腫大が尿道の内腔を圧排し、排尿に時間がかかる前立腺肥大症を発症したります。
一方で、女性では出産や加齢のために、尿道や膀胱を筋肉が支えきれなくなり過活動膀胱や尿失禁を来したり骨盤臓器脱を起こしたりします。
また、原因疾患もたくさんあります。同じ症状であっても対処方法が異なってくることがありますので、専門施設で検査を行い、しっかり診断することによって正しい治療ができ、早く症状が改善することが期待できます。
排尿障害の症状
排尿障害の症状は実に様々で、以下のように分けられます。
| 蓄尿障害 | 排出障害 | |
|---|---|---|
| 蓄尿症状 | 排出症状 | 排尿後症状 |
|
|
|
蓄尿症状
十分に膀胱内に尿を貯められない状態のこと。
1. 昼間頻尿
日中起きている間に8回以上排尿すること。
2. 夜間頻尿
夜間睡眠中に1回以上排尿のために起床すること。
3. 尿意切迫感
突然起きる抑えきれない尿意のこと。尿意でトイレに慌てて駆け込む状態。
4. 遺尿症
昼夜を問わず、自分の意思と無関係に尿が出てしまうこと。特に夜間にのみ起こることを夜間遺尿症(夜尿症)といいます。
5. 尿失禁
そのタイプによって様々な状態がありますが代表的なものは以下の5つです。
- 腹圧性尿失禁
咳やくしゃみ、重いものを持ったときに尿が漏れる状態のこと。 - 切迫性尿失禁
尿意切迫感の結果として尿が漏れること。 - 混合性尿失禁
腹圧性と切迫性を両方とも併せ持つ状態のこと。 - 機能性尿失禁
膀胱などの機能は正常であるにも関わらず、トイレまでの移動や脱衣までに時間を有することで失禁を起こすもの。 - 溢流性尿失禁
十分排出できず膀胱内に多量に残った尿がぼとぼととあふれて出てくること。
排出症状
尿の排泄が十分行えない状況のこと。
1. 尿勢低下
尿の勢いが弱いこと。
2. 尿線分割/尿線散乱
尿が1本でなく2本にわかれたり、飛び散ったりすること。
3. 尿線途絶
排尿の途中で尿線が途切れること。
4. 排尿遷延
尿が出はじめるまでに時間がかかること。
5. 腹圧排尿
排尿時にお腹に力をいれ、息んで排尿すること。
6. 終末滴下
排尿の終わり頃に尿がぼとぼとと垂れること。
排出後症状
排尿後に出現する症状のこと。
1. 残尿感
排尿後まだ尿が残った感じがすること。
2. 排尿後尿滴下
排尿後下着をつけてから尿が少し漏れてくること。
排尿障害の診断
初診時には特に詳細な問診と、症状に応じた検査を行い的確な診断を行います。
一般的な診断方法には以下のようなものがあります。
| アンケートを用いた症状の評価 | (国際前立腺症状スコア、過活動膀胱症状スコア、尿失禁症状・QOL評価質問票) アンケート調査を行うことで、聞き漏れがなく症状の把握ができ、症状の重症度も評価できます。 |
|---|---|
| 排尿日誌 | 3日間程度、①排尿時間、②排尿量、③飲水量、④失禁の有無などを日誌に記載していただきます。自宅での排尿習慣を把握します。 |
| 尿検査 | 膀胱炎などの感染やがん等の悪性腫瘍がないことを確認します。 |
| 採血 | 腎機能障害がないか、また男性では前立腺がんの可能性がないかPSA(前立腺特異抗原)を測定します。 |
| 超音波検査 | 尿をしっかり排出できたか残尿量を測定したり、水腎症といって腎臓の腫れがないかどうかを調べます。そのほか超音波検査では、前立腺肥大の程度を調べるために体積を測定したり、腎臓や膀胱などに悪性腫瘍がないかどうかも調べることができます。放射線被ばくはなく安心して検査を受けていただけます。 |
泌尿器科で専門的な検査には以下のようなものがあります。
1. 尿流動態検査
尿流測定検査
検査用のトイレに排尿していただき、その時の排尿量や勢いを測定します。残尿測定とセットで行います。

内圧流量検査
神経因性膀胱の診断や前立腺肥大症、尿失禁などの評価目的に行います。尿道や肛門に検査用の細い管(カテーテル)を挿入する必要がありますが、排尿サイクル全体での膀胱、尿道の機能全般が評価可能です。

尿流動態検査に使用する機械

内圧流量検査
2. 鎖膀胱尿道造影
特に女性に多い骨盤臓器脱や尿失禁の患者さんに行います。尿道から特殊な機械と造影剤を注入し、骨盤臓器脱の程度や尿道の状態を把握します。造影剤を血管内に注射するわけではありませんので造影剤アレルギーがある方でも施行可能です。

骨盤臓器脱(膀胱瘤)の症例
膀胱が恥骨結合下縁より大きく下がっている。
排尿障害の治療
手術以外の排尿障害の治療法には、
- 保存的療法
- 薬物療法
があります。
保存的療法には食事制限や減量などの生活指導、骨盤底の筋力強化をめざした骨盤底筋訓練などの理学療法、膀胱容量の拡大をめざした膀胱訓練を中心とした計画療法などがあります。
1. 保存的療法
生活指導
排尿障害、特に前立腺肥大症、過活動膀胱、尿失禁などの原因として肥満、糖尿病、飲水過多、過剰な食事摂取、喫煙、便秘が挙げられます。これらの改善は症状を緩和するために非常に重要なことです。
生活指導を行った患者さんでは行わなかった患者さんより明らかに症状が改善します。
効果があると思われる生活上の注意点
- 減量(食事制限、運動)
- 過剰な水分や塩分摂取をしない
- 禁煙
- 便秘の改善
理学療法
骨盤底筋訓練
骨盤底筋群の収縮力を増強させる非侵襲的な治療法です。具体的な方法としては坐位や立位、仰臥位など様々な体位で行い、「腟を体の中にひっぱりこむように腟や尿道を締める」、「おならを我慢するような感じ」などのイメージで行います。1セットは10回程度で、毎日5セット程度行います。
計画療法
膀胱訓練
排尿を我慢し頻尿を改善させる治療法。効果の発現には時間がかかります。尿意切迫感を自覚してから排尿するまでの間を5分、10分、15分と少しずつ伸ばしていきます。
2. 薬物療法
排尿機能改善薬は、
- 膀胱に貯まった尿を出しやすくする薬剤
- 膀胱の蓄尿機能を改善する改善
- その他尿失禁や主に自覚症状を改善する薬剤
等にわけられます。
排尿障害改善薬
主なものには、α1受容体遮断薬、PDE5阻害薬、5α還元酵素阻害薬があります。
| 薬剤 | 作用の仕方 | 特徴 |
|---|---|---|
| α1受容体遮断薬 |
|
|
| PDE5阻害薬 |
|
|
| 5α還元酵素阻害薬 |
|
|
蓄尿障害改善薬
主なものには、抗コリン薬やβ3受容体刺激薬があります。
| 薬剤 | 作用の仕方 | 特徴 |
|---|---|---|
| β3受容体刺激薬 |
|
|
| 抗コリン薬 |
|
|
その他の薬剤
腹圧性尿失禁に対するβ2受容体刺激薬や、自覚症状改善を目的とした植物製剤や漢方薬などがあります。
各薬剤1種類だけを使用するのではなく、重症な症例では、お薬を増量したり、併用したりと工夫して治療していきます。
また、上記薬剤を使用しても改善が乏しい場合は、ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法や、仙骨神経刺激療法(下記手術療法を参照)も治療の選択肢となります。
3. 手術療法
処方薬による治療で効果を認めない場合には下記のような手術療法を選択することがあります。
| 前立腺肥大症 | |
|---|---|
| 腹圧性尿失禁 |
経閉鎖孔テープ留置術(TOT) 経膣テープ留置術(TVT) |
| 骨盤臓器脱 | |
| 過活動膀胱 |
ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法 仙骨神経刺激療法 |