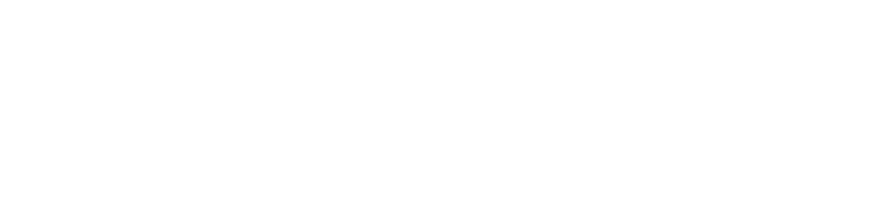小児泌尿器科疾患
小児泌尿器科疾患とは
小児泌尿器科疾患のほとんどが良性疾患であり、お子様の成長と共に自然に良くなる疾患も多い一方で、生活に支障をきたすために泌尿器科的な治療や管理が必要になる疾患も含まれています。その代表的な疾患として、停留精巣や尿道下裂、膀胱尿管逆流、水腎症、膀胱直腸機能障害、尿路感染症、夜尿症、昼間尿失禁などが挙げられます。
小児泌尿器科疾患の症状
個々の疾患によって症状は多彩ですが、小児泌尿器科疾患でよくみられる症状や訴えとして「精巣が陰嚢の中に下りていない」、「おしっこの出口が通常と異なる」、「おちんちんの皮が脹れて赤くなっている」、「おしっこが原因で熱を繰り返している」、「おしっこに行く回数が少ない」、「日中も夜もおしっこが漏れている」、「腰背部を痛がり、嘔吐することがある」などがあります。
小児泌尿器科疾患の診断
小児泌尿器科疾患の診断では、主に身体診察や検尿、超音波検査といった体に負担のない方法を用いることが多いのですが、疾患の状態や治療の適応を判断するために排尿時膀胱尿道造影(VCUG)や腎シンチグラフィーなど侵襲的な検査が必要になることがあります。さらに全身麻酔を併用して膀胱尿道内視鏡検査や逆行性腎盂造影を行うこともあります。また、MRIやシンチグラフィーといった画像検査では撮影時の安静が必要不可欠であり、安静を保持できない場合には鎮静下で検査を行います。
小児泌尿器科疾患の治療
小児泌尿器科疾患は成長とともに自然に良くなることも多いため、治療が不要な場合も少なくありません。そのため、本当に治療が必要な状況なのかどうかを見極めることがとても重要になってきます。たとえば、生まれた直後に水腎症と診断されたとしても、その大半が一過性で生理的な水腎症であるため、自然に改善することが期待できます。水腎症だからといって直ちに治療が必要というわけではなく、定期的に経過を見ていく中で本当に治療が必要な状態なのかを判断してくことになります。当科では年間70-80例の全身麻酔下手術(検査も含む)を実施しています(手術内容については下記をご参照ください)。
当科で実施している主な手術
停留精巣固定術・包皮環状切除術・埋没陰茎根治術・顕微鏡下精索静脈瘤手術・尿管膀胱吻合術(膀胱尿管逆流手術)・腎盂形成術など
小児泌尿器科疾患における長崎大学病院の役割
当院は小児泌尿器科疾患を専門とする医師が常勤する県内唯一の大学病院として、小児泌尿器科疾患の治療のみならず、小児科や小児外科、産婦人科、整形外科、脳神経外科といった他の診療科とも連携しながらお子様の健やかな成長をサポートいたします。