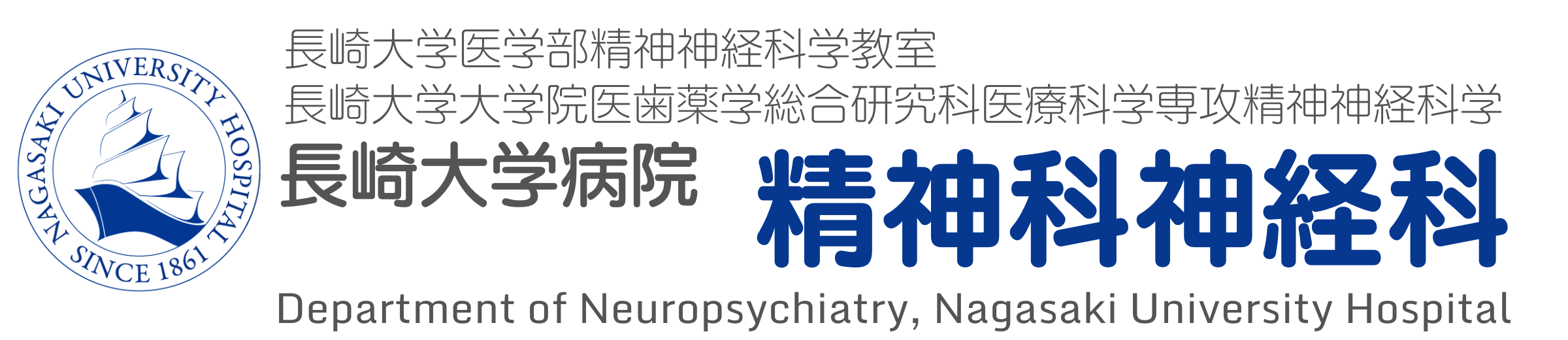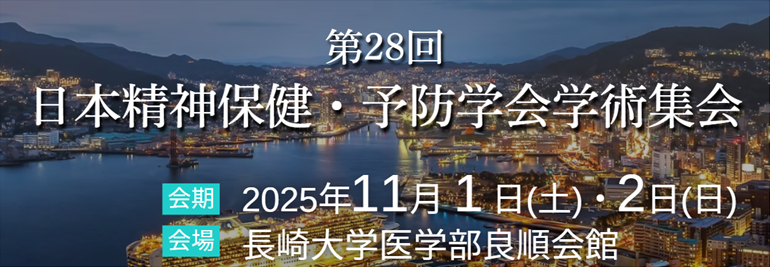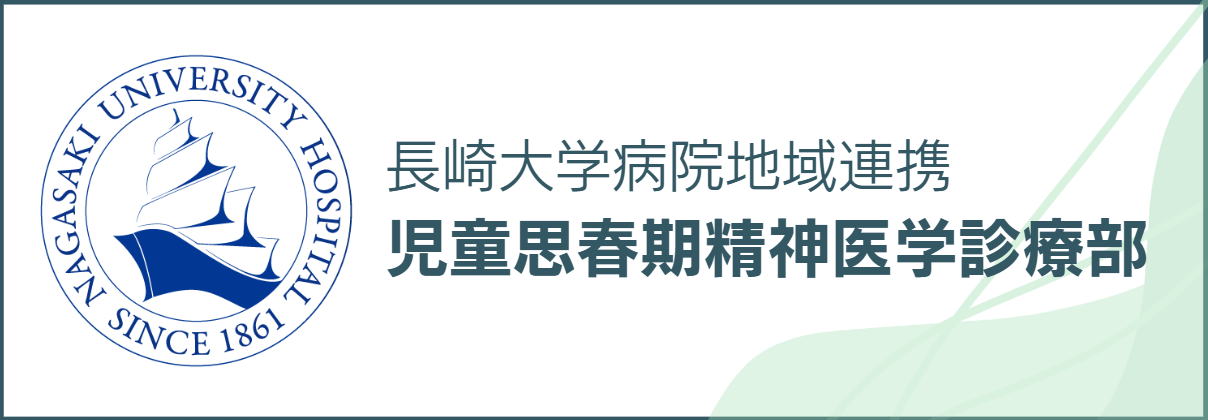研究ニュース
■ 熊崎教授の業績をまとめました(2025年09月05日)
■ 論文がアクセプトされました(2025年8月13日)
- Urashima K, Ichinose K, Ishimaru H, Kumazaki H, Kawakami A, Ueki M. Novel imaging diagnosis of neuropsychiatric systemic lupus erythematosus using topological data analysis: A retrospective study. PLoS One. 2025 Aug 13;20(8):e0329859. doi: 10.1371/journal.pone.0329859. PMID: 40802600; PMCID: PMC12349068.(IF: 2.6)
- 渡辺 博之先生(研修医)が、「無床精神科総合病院における急性薬物中毒患者についての検討」の演題で発表しました
- 藤川 真莉子先生(研修医)が、「初期研修中に精神科と感染症内科の両科で多様な精神症状を呈した梅毒症例を経験して考察が深まった一例」の演題で発表し、優秀発表賞を受賞しました
- 好川 周作先生(研修医)が、「ソーシャルアバターの使用が自閉スペクトラム症者の社会的コミュニケーションに及ぼす影響」の演題で発表し、優秀発表賞を受賞しました
- 佐藤 志帆先生(研修医)が、「精神科デイケアでの自律対話ロボットを活用した対話プログラムの実践報告」の演題で発表し、優秀発表賞を受賞しました
- 長谷川 達郎先生 が、「モーズレイ神経性やせ症治療を元にした認知行動療法的アプローチで外来に移行できた重症神経性やせ症の一例」の演題で発表し、優秀発表賞を受賞しました
- 髙尾 彰哉先生が、「病態の再評価によりベンゾジアゼピン系薬剤依存の背景にパニック障害があることが判明し、治療に至った一例」の演題で発表しました
- 夏山 竜一先生が、「間歇型一酸化炭素中毒による遅発性脳症に対して塩酸ドネペジルを投与し、認知機能と運動機能が回復した一例」の演題で発表しました
- 大橋 愛子先生が、「せん妄治療薬に関する臨床意思決定支援システム(CDSS)プロトタイプの開発とその可能性」の演題で発表しました
- 冠地 信和先生が、「統合失調症スペクトラム障害患者に実施したアバターを介した社会参加支援」の演題で発表しました
- 清水 日智先生が、「アクチグラフを用いた自閉スペクトラム症児の問題行動に寄与する睡眠障害の解明」の演題で発表しました
- 酒井 慎太郎先生が、「生活史健忘と別人格の固定化のため、性別不合を訴えてホルモン療法を求める若年男性の一例」の演題で発表しました
- 浦島 佳代子先生が、「トポロジカルデータ解析を用いた神経精神ループスの診断精度向上のための臨床研究」の演題で発表しました
- 熊崎 博一先生が、シンポジウム「2050年の我が国における児童思春期精神科医療の展望」「長崎県におけるヒューマノイドロボットを用いた遠隔診療の実践」「児童精神医学においてヒューマノイドロボットが果たすべき役割」「長崎大学医学部精神神経科学教室における児童精神科医の育成」「発達障害臨床におけるロボット導入の意義」で発表しました
- 塚崎 遼先生(医学部生)が、「SSRIによる解離症状の顕在化と支持的介入による改善を認めた解離性障害の一例」の演題で発表しました
- Hirokazu Kumazaki. Intervention Using Android Robot for Individuals with Autism Spectrum Disorders. International Society for Autism Research (INSAR). Seattle. USA. 2025.4.
- Hirokazu Kumazaki, Yoshimasa Ohmoto, Kensuke Tazoe, Hitomi Shimizu, Yurie Teshima, Kazunori Terada, Ryoichiro Iwanaga. Shape Drawing As a Potential Screening Technique for Children with Autism Spectrum Disorder. International Society for Autism Research (INSAR). Seattle. USA. 2025.4.
- Hitomi Shimizu, Aiko Ohashi, Kensuke Tazoe, Kazunori Terada, Ryoichiro Iwanaga, Hirokazu Kumazaki. Elucidation of the Relationship between Sleep Disturbance and Sensory Characteristics Leading to Behavioral Problems in Children with Autism Spectrum Disorder. International Society for Autism Research (INSAR). Seattle. USA. 2025.4.
- Hirokazu Kumazaki, Yurie Teshima, Yuichiro Yoshikawa, Akira Utsumi, Takahiro Miyashita, Hiroshi Ishiguro. Communication Training Using a Social Avatar for Young Adults with Autism Spectrum Disorders. International Society for Autism Research (INSAR). Seattle. USA. 2025.4.
■ 2025年03月13日~03月14日 第43回日本社会精神医学会
- 谷保康一先生が、「知的発達症の養育者の下で脳幹脳症の重篤な後遺症を生じ、その後の支援が困難であった知的発達症の若年女性への社会的介入の報告」の演題で発表しました。
- 志方有莉先生が、「精神科デイケアの統合失調症患者1例に実施した、自律対話ロボットCommUを活用したソーシャルスキルトレーニングの試み」の演題で発表しました。
■ 2024年11月29日~11月30日 第37回日本総合病院精神学会学術総会
- 岩永健先生が、「リチウム中毒後 構音障害が残存するSILENTを発症しリハビリ後に改善を認めた一例」の演題で発表しました。
■ 2024年11月28日~11月29日 第76回九州精神神経学会
- 城田理恵先生が、「20年間うつ病と診断されていた双極性障害に対し炭酸リチウムが著効した1例」の演題で発表しました。
- 髙尾彰哉先生が、「短期的かつ集中的な入院による依存症治療が奏功した1例」の演題で発表しました。
■ 2024年10月17日~10月19日 第65回日本児童青年精神医学会総会
- 熊﨑博一先生が、シンポジウム「長崎大学病院地域児童思春期診療部における児童精神科医の育成」「味覚特性・偏食研究からみえてくるASD者の感覚特性」で発表しました。
- 清水日智先生が、「自閉スペクトラム症児の感覚特性と睡眠に関する全国調査」の演題で発表しました。
- 川原紘子先生(道ノ尾病院)が、「片足立ち評価を通じた自閉スペクトラム症の定量的スクリーニングモデル開発」の演題で発表しました。
- 田添健裕先生が、「自閉スペクトラム症スクリーニングにおける機械学習を用いた図形描画評価の可能性」の演題で発表し、優秀発表賞(若手部門)を受賞しました。
- 藤原伸治先生(研修医)が、「自閉症スペクトラム児の感覚と睡眠障害の関連」の演題で発表し、優秀発表賞(若手部門)を受賞しました。
■ 2024年6月20日~6月22日 第120回日本精神神経学会学術総会
- 熊﨑博一先生が、シンポジウム「最新のテクノロジーを用いたギフテッド特性を考慮した精神科患者支援」「自閉スペクトラム症者のprosodyに着目する理由」「長崎県での遠隔操作ロボットを用いた精神科患者支援」「デジタル技術を用いたうつ病患者支援」「精神科治療を目指したロボット研究の現状」で発表しました。
- 大石佳奈さん(長崎大学医学部学生)が、「統合失調症患者へのCG ロボット(CGCommU)を用いたオンライン対話の有用性についての検討」の演題で発表しました。
- 小川実里先生(研修医)が、「初対面の場における発達障害者の対人スキル向上のためのアバター活用社会参加支援の実際」の演題で発表し、優秀発表賞(初期研修医・学部学生部門)を受賞しました。
- 手島由利恵先生が、「多彩な精神症状を呈した抗NMDA受容体抗体陽性の抗MOG抗体関連疾患の皮質性脳炎」の演題で発表しました。
- 清水日智先生が、「自閉スペクトラム症児の感覚特性と睡眠に関する全国調査」の演題で発表しました。
- 冠地信和先生が、「遠隔操作型ロボットを用いた離島診療支援の予備的研究」の演題で発表しました。
- 夏山竜一先生が、「不眠、幻視等を呈した女児に対して、精神科リエゾン介入により可逆性後頭葉白質脳症の発見に寄与した症例」の演題で発表しました。
- 中村康司先生(県精神医療センター)が、「統合失調症との鑑別に難渋したSLEの一例」の演題で発表しました。
- 大橋愛子先生が、「重症遷延性神経性やせ症で治療に難渋した2症例」の演題で発表しました。
- 山本直毅先生が、「高リスク、あるいは低リスクのギャンブル行動についての示唆的考察(長崎県の令和2年度調査を踏まえて) 」の演題で発表しました。
■ 2024年4月 冠地信和先生が、日本社会精神医学会で優秀発表賞を受賞しました
- 第42回日本社会精神医学会「離島で実施した、遠隔操作型ロボットによる精神科診療支援の2症例」の演題で、優秀発表賞を受賞しました。
■ 2024年3月 中根允文名誉教授が、第1回日本社会精神医学加藤正明賞を受賞しました
- 社会精神医学領域の進歩、発展、普及等において長年にわたり優れた功績を挙げたとして「日本社会精神医学加藤正明賞」を受賞されました。
■ 2024年3月 山本直毅先生が、大学院を卒業し博士号を取得しました
- 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科医療科学専攻をご卒業しました。
■ 2024年3月13日~15日 第42回日本社会精神医学会
- 熊﨑博一先生が、教育講演「児童精神医学にデジタル診療が果たす役割」、シンポジウム「バーチャルリアリティ技術を用いた発達障害者支援」で発表しました。
- 佐藤志帆さん(長崎大学医学部学生)が、「精神科デイケアでのヒューマノイドロボットを介した対話プログラムの実践報告」の演題で発表しました。
- 大石佳奈さん(長崎大学医学部学生)が、「アルコール依存症患者へのCGロボット(CGCommU)を用いたオンライン対話の有用性についての検討」の演題で発表しました。
- 小川実里先生(研修医)が、「統合失調症患者の社会参加支援の可能性が広がるアバターシステムの開発についての予備的研究」の演題で発表しました。
- 冠地信和先生が、「離島で実施した、遠隔操作型ロボットによる精神科診療支援の2症例」の演題で発表しました。
■ 2023年11月17日~18日 第36回日本総合病院精神医学会総会
- 田添 健裕先生が、「筋強剛、発熱、CK上昇を認め悪性症候群と悪性緊張病の鑑別に苦慮した一例」の演題で発表しました。
■ 2023年11月14日~16日 第64回日本児童青年精神医学会総会
- 熊崎 博一先生が、「児童精神科領域におけるロボットを用いた支援の可能性」の招待講演、「AIを用いた5歳児健診の潜在性」のシンポジウムで発表しました。
- 清水 日智先生が、「クラウドソーシングを用いた自閉スペクトラム症児の睡眠と発達に関する研究」の演題で発表しました。
- 山本 直毅先生が、「潜在的なゲーム行動症のリスクと、ゲームを構成する要素の示唆的考察「COVID-19 パンデミックにおける休校後の、長崎県の児童・生徒におけるゲームに関連した行動様式の横断的調査」を踏まえて」の演題で発表しました。
■ 2023年10月19日~20日 第75回九州精神神経学会
- 手島 由利恵先生が、「歩行障害を伴う認知症との鑑別を要した重症うつ病の一例」の演題で発表しました。
- 夏山 竜一先生が、「アセナピンマレイン塩酸塩の口腔内投与により接触性皮膚炎を生じた症例の共有」の演題で発表しました。
■ 2023年6月22日~24日 日本精神神経学会学術総会
- 熊崎 博一先生が、「発達障害診療におけるロボット支援の可能性」「ヒューマノイドロボットを用いたギフテッド者への支援」「長崎県における離島・へき地支援」「自閉スペクトラム症者への嗅覚特性を考慮した支援」のシンポジウムで発表しました。
- 今村 明先生が、「産業精神医学における神経発達症の感覚特性支援」「ICD-11/DSM-5-TRから児童青年期精神医学の診断の近未来を考える」のシンポジウムで発表しました。
- 木下 裕久先生が、「長崎大学病院における新型コロナウィルスに関連する職員のストレス状況調査と心理的支援 第3報」の演題で発表しました。
- 冠地 信和先生が、「デイケア利用者が遠隔操作型ロボットに抱く信頼感に影響を与える条件について比較検討したので報告する」の演題で発表しました。
- 山本 直毅先生が、「長崎県における児童精神科医療へき地支援体制の構築」のシンポジウムで発表しました。
- 川原 紘子先生が、「遠隔操作型ロボット(Sota100)を用いた産休育休中の医師支援についての予備的研究」の演題で発表し、優秀発表賞を受賞しました。